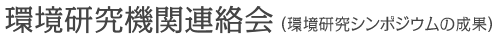第7回環境研究機関連絡会成果発表会
基調講演
アジア農業の生態リスクと食糧安全保障のゆくえ
―環境と農業とのかかわりをどう見直すか―
| 講演者:横浜国立大学 大学院 教授嘉田 良平 |
講演内容
1.21世紀・食料問題の構図はどうなるの
環境問題とならんで、食料問題は21世紀前半における人類の最重要課題と位置づけられている。主に二つの理由からである。ひとつは、第二次大戦後の驚異的な農業技術進歩にもかかわらず、世界の栄養失調人口(あるいは飢餓人口)はいっこうに減らず、最近、ついに10億人という大台を突破した(FAO2009年推計)ことである。もうひとつは、食料生産に対する地球温暖化、その他の気候変動の影響、バイオ燃料向け農業生産との競合、感染症など新たな食料リスクの拡大が顕在化しつつあり、将来に向けて暗い影をおとしているからである。
そこで以下、20世紀における農業と環境とのかかわりを振り返りつつ、今後の展望あるいは見直しの方向について述べる。農業は本来、自然の力を最大限に生かし、物質循環のメカニズムを取り込むことによって環境保全に寄与しうる産業であるが、20世紀後半に入って、先進国の農業は化学資材をより多投入し、大型機械によって単作化を進めてきたため、自然環境や生態系に対する負荷を増大させることになった。
実際、20世紀半ば以降、急速に生産性を伸ばしてきた農業の拡張は、産業廃棄物を排出し続ける工業とならんで、地球環境悪化の一つの原因となってきた。高い人口圧力の下で農地を拡大すれば森林や草原の消滅をもたらし、それは地球の温暖化や野生生物種の絶滅につながる。過耕作や過放牧は土壌侵食や砂漠化を招き、不用意な灌漑農業は塩類化によって農地の荒廃をもたらす。また、農地から揮散するアンモニア、亜酸化窒素、メタンなどのガスは地球温暖化、オゾン層の破壊や酸性雨の原因の一部となる。その結果、世界各地で砂漠化、塩害、土壌劣化など、農業そのものの持続可能性が徐々に失われることになる。
先進国における大規模で機械化の進んだ商業的農業においては、単作化や連作にともなう化学資材の多用、エネルギー集約的な農法の採用によって、土壌侵食や水質汚濁、地下水の枯渇、食品安全性に対するリスク増大など、さまざまな問題を引き起こしてきた。わが国においても、単作・連作化に起因する過剰施肥や農薬の過剰な投入、多頭飼育による畜産からの廃棄物など、農業が環境に及ぼす影響はすでに各地で重大な課題として問われてきた。
他方、開発途上国においても、過耕作や過放牧に起因する土壌侵食や砂漠化によって生産力を失いつつある農地面積は、毎年、数百万ヘクタールに上っている。さらに、農村の貧困化は都市への貧民の流入を引き起こし、社会不安を増大させている。
こうして世界的に食料危機の到来が叫ばれる一方で、日本では農業の衰退が懸念されている。農家は後継者の不足に悩み、農地条件の不利な多くの中山間地域では耕作放棄地が増加し続けている。はたして、これで日本農業は大丈夫なのか、あるいは私達の食卓は本当に安心できるのであろうか。
2.食糧安全保障のパラダイム転換
21世紀の食糧安全保障の特質を、私は「パラダイム転換」と呼ぶことにしている。パラダイムの転換とは、基礎的な条件、規範そのものが大きく変わりつつあるという意味である。20世紀には問題とならなかった条件が変化して、21世紀の今、我々の前に大きく登場しており、それがこれまでにない困難な問題を引き起こしている。20世紀においては需給バランスによる問題、つまり量的に食料が不足するという歴史的な問題が中心であったが、21世紀に入って、食の分野に新しい困難な要素が加わったのである。とくに三つの条件変化に注目したい。
第1は、地球温暖化による食料供給面への悪影響である。特にその影響は貧困層に対してより大きな影響をもたらす。地球温暖化を中心とする気候変動。IPCCは2007年、第4次評価報告書を出して、この問題を取り上げた。要は気温の上昇だけでなく降雨パターンが大きく変わることがポイントである。それによって農業生産が大きくダメージを受ける。その中でも、コメは比較的影響を受けやすい農産物であると言われている。農水省によれば、西日本の稲作では最大40%の減収が予測されるとしている。地球規模の影響で食料輸入はこれまでと同じように続けられるであろうか。オーストラリアや北米での水不足は、すでに目前に迫っている。水不足によって、近年、オーストラリアには米の輸出余力はもはやないのである。地下水位の低下が止まらないからである。
第2の条件変化は、食料のバイオ燃料への転換である。これまでも食料の一部は燃料として使われることがあったが、それは量的にも少なく、食料供給を脅かしたり、食料価格を高騰させるということはなかった。だが、バイオ燃料用のプランテーションの拡大はアジア、アフリカ諸国で1990年代後半から急増し、食料供給を削減させ、生物多様性はじめ生態環境を破壊するという副作用をもたらすことになった。つまり、バイオ燃料の登場はもうひとつの食料問題、そしてもうひとつの環境問題を人類に突きつけることになった。バイオ燃料の登場は、食料か燃料かをめぐる農産物の争奪戦が、まさに地球規模で開始されたことを意味している。つまり、バイオ燃料というエネルギー問題が食料問題とリンクされてきたのだが、まさにパラダイム転換とも呼ぶべき大きな変化である。
第3は、食品安全面でのリスクの拡大であるが、これも人類にとっては古くて新しい課題である。O-157(腸管出血性大腸菌)、鳥インフルエンザ、BSEなど、食に深く関係する感染症の国際的な拡大が、食品のリスクを増大させてきたことは周知の通りである。食品の冷蔵・冷凍技術の向上に加えて、経済のグローバル化によって食品のリスクはあっという間に国境を越え、さらに拡大するという構図となってきた。このように、食料の安全保障はまさに量と質の両面から揺らぎつつある。質の面では、農産物や食料の安全性に対する懸念が強まったのであるが、先進国ではおしなべて食品安全性の確立が最優先課題として取り組まれてきた。
以上のように、二十世紀においてほとんど心配する必要のなかった前提条件が大きく崩れ、我々の前に新しい壁として立ちはだかっている。これがパラダイムシフトである。しかも、それら三つの条件変化への対応は待ったなしの状況にある。それは、需給の逼迫という一般的な危機に加えて、食糧安全保障を脅かす新しい課題だからである。
3.バイオ燃料か食料か ~インドネシア・スマトラ島での調査より~
バイオ燃料の登場は、エネルギー問題が食料問題に大きく影響するという、これまでにない新しい構図をつきつけている。アジアではマレーシアやインドネシアで、中南米・ブラジルやアフリカ諸国において、バイオ燃料増産のために新しくプランテーションが造成され、作付転換が行われている。だが、プランテーション造成のために貴重な熱帯雨林が次々と焼かれる光景は、いったい何のためのCO2削減なのかと目を疑うばかりである。バイオ燃料は本当にCO2の削減に貢献するのかどうか、生産・加工・流通すべてを考慮した上での検証が不可欠である。
2007年5月23日、(独)農業環境技術研究所の主催により、レスター・ブラウン氏を招いたシンポジウム「食料か燃料か~穀物の争奪戦が始まった~」が東京都内で開催され、パネリストの一人として私も招かれた。
地球環境問題に警鐘を鳴らし続けてきたブラウン氏は、「バイオ燃料の需要拡大によって食料問題は一層深刻化するであろう」と今後の見通しを述べた。「原料となる食料の価格がさらに上がれば、貧しい国の人々の暮らしに深刻な影響をもたらす」「市場原理だけに任せて食料を車の燃料に使ってよいのか」「バイオ燃料の工場の新設は一時凍結すべきだ」と氏は訴えた。
私は、「バイオ燃料の生産と貿易において守るべきルール」として、次の三原則を提案した。①生産・加工・輸送プロセスでCO2排出量を増加させないこと、②農地転用、森林伐採等による生態系の破壊、土壌劣化など、新たな環境破壊を引き起こさないこと、そして、③主食の確保という観点から零細農民や貧困層の食料安全保障を脅かさないこと、である。
貧しい人々から食料を奪ったり、地球環境を破壊してまで、「食料を燃やす」だけの余裕は現代の地球にはないはずである。もちろん、化石燃料と比較すればバイオ燃料の方が環境面ですぐれていることは明らかである。ただし、貧しい人たちから食料を奪うという食料安全保障上の問題に加えて、土壌劣化や生態系の破壊という環境問題の側面から、バイオ燃料は今後とも注視せねばならない。
では、途上国の生産現場ではどのような問題が起きているのか。私は、2008年以来、数度にわたってインドネシア・スマトラ島での現地調査を行う機会を得た。マレーシア、インドネシアなどでは急速にバイオ燃料用プランテーションが拡大し、農林地の乱開発に伴う野焼き、土壌流出、生態系破壊など新たな環境問題が深刻化している。以下は、その時の印象記である。
最大の問題は、食料安全保障に対して、バイオ燃料の登場はかなり影響しているという点であろう。インドネシアやマレーシアでは、バイオ燃料用プランテーションの造成の為に山に火をつける。その前に太い木を用材として切る。火をつけて森林火災を人為的に起こした後、油ヤシの苗木を植えるのである。火をつければ儲かるというブームゆえに、森林に火をつける。しかし、自分達の食べる主食や畑作物を犠牲にしてバイオ燃料に走るのだけれども、それで所得が増えるわけではないという。プランテーションの所有者はたいてい外国資本で、地元住民に所得が大きく分配されるようにはなっていないのだ。
自らの畑や森を焼き払って、バイオ燃料のプランテーションへと転換する。問題は、その過程で排出される巨大なCO2の量である。このような土地利用の変化によって、つまりインドネシアの野焼きと熱帯土壌が乾燥することによって排出されるCO2の総量は、年間約7億トンと推計されている。日本全体で年に約13億トンであるので、その半分以上の量に匹敵するCO2の量が泥炭湿地から出ていることになる。実は、インドネシアやマレーシアは隠れたCO2の一大排出国となっているのである。バイオ燃料への転換がその最大の理由である。
スマトラ島での現地調査の際、あちこちで集落道や農地が水浸しになるという光景にぶつかった。2008年6月のことであったが、乾季なのに数日間雨が降り続き、道路が冠水してしまったのである。このような異変が近年、日常的に起きていると聞いた。コミュニティでの生活にも大きな支障が生じている。当然、その社会的なコストは巨額なものであろう。貴重な農地すら冠水状態となり、水没して使えないという。環境破壊に加えて、零細農家や貧困層への影響は計り知れない。プランテーションの経営はほとんどが資金力のある外資系の資本である。ただし、利益は地元には還元されないようだ。
4.アジア農業の生態リスクと食料需給の長期見通し
次に、これからの食料需給の見通しについても述べておきたい。20世紀の半ばから始まった人口爆発ともいうべき急激な人口増加の中で、発展途上国では耕境の外延的拡大と単位収量の増大によって食料を確保してきた。先進諸国では、畜産物偏重への食生活パターンの変化がオリジナルカロリー消費の増大を引き起こし、これに対応するため、化学資材およびエネルギー多消費型の農業の集約化によって食料増産をし続けてきた。
このような懸命な努力の結果、世界の農業・水産業は増大する人口をほぼ養うことができた。しかし、飢餓や栄養失調に苦しむ人口は、近年、ふたたび急上昇し始めた。人類は全体としては、食料不足の不安から決して解放されていない。食料問題の焦点とされる中国やインドにおいては、農地の拡張が基本的にはこれ以上望めないこと、化学資材の増投が単収の伸びにほとんどつながらなくなってきたこと、水不足あるいは低湿地での土壌浸水、塩害、砂漠化などに見られる水資源の制約が各地で顕在化しつつある。
環境問題の深刻化、そして資源の劣化・喪失という「生態リスク」がさらに拡大するという条件のもと、人口増加と食料需要の増大に対して、はたして地球が養っていけるのであろうか。全く予断を許さなくなってきた。国連食糧農業機関(FAO)の推計によれば、増え続ける発展途上国の人口を養うためには二十一世紀の第1四半期に現在の五倍程度の穀物増産が必要となると予測している。だが、楽観的に見積もっても、世界全体で2025年までに増やせる農地は1億ヘクタール以下であり、必要とされる農地拡大面積(1.75億ヘクタール)の半分程度に過ぎない。
近年、アジア農業・漁業の現場において生態系の破壊、食品汚染、水質汚染、洪水の多発などさまざまな異変が生じている[嘉田編「アジアで拡がる生態リスクと食料安全保障問題」2008横浜国立大学]。そのほとんどは森林破壊や土地改変など人為的な活動に起因するものであり、生態系サービスの低下・劣化と捉えられている[UNEP「ミレニアム生態系評価」2005]。しかも、こうした生態系の劣化は、多くの場合、「食のリスク」(食料安全保障および食品安全にかかわる諸問題)の拡大につながっており、人々の栄養・健康問題をはじめとする「貧困と環境の悪循環」をもたらしている。それゆえに持続可能な発展を実現するためには、生態系の劣化に適応しうる「食」と「農」にまたがる統合的・順応的なリスク管理(「食・農リスク管理」と呼ぶ)がきわめて重要であり、上流山間部から下流沿岸域に至る流域圏を単位として対応・設計する必要がある。
しかし、生態系の劣化問題と食のリスク拡大との因果関係は、これまで学術的にほとんど明らかにされてこなかった。その理由として、生態系サービスの多くが外部経済効果であり市場で取引されないため、経済的な評価がほとんど行われなかったこと、そして、食のリスクが一般的に長期的な累積の結果あるいはタイムラグを伴うために因果関係の特定化が困難であることが指摘されている。経済のグローバル化が進む中で、フードマイレージの拡大とともに、環境負荷の連鎖は、国際的スケールで捉えるべき時代を迎えている。上流・下流間そして国際間の「環境トレーサビリティ」あるいは「環境支払い」が求められるのではなかろうか。そのためにも、生態系サービスの劣化について定性的かつ定量的に把握するとともに、持続可能な再生・回復の道筋を具体的に提示することが必要である。
5.里山・生物多様性の価値と地域再生 ~「環境支払い」の課題と条件~
本来なら、もっとも自然環境と調和し、共存すべき産業であるはずの農林水産業の持続可能性が、いま世界各地で失われつつある。農地、水資源、そして生物多様性など、農林水産業が依拠する根源的な自然資源が失われたり、破壊されるリスクが高まっているからである。農林水産業と自然環境の保全はいかに両立するのか。自然資源をいかに保全・管理すべきか、健全な形で次世代に繋げるのか、そして、誰がコストを負担するのかなど、多くの課題が横たわっている。
水田の生態系は水田そのもの、畦畔、水路、ため池、周囲の屋敷林、里山などから構成される。この水田生態系こそが、実はきわめて多様な生態系と豊かな農村空間を形成してきた。赤とんぼやメダカなど、さまざまな生き物が、数千年の水田稲作と農村の暮らしに適応することを通して生き続けてきたのである。大切なのは、水田の生物多様性や農村景観が自然な状態で存在するのではなく、長年にわたる人々の農業の営みあるいは暮らしを通して維持されてきたことである。
私はかつて、水田の生物多様性のもつ社会経済的価値として、次の4点を指摘した(農業環境技術研究所編『水田生態系における生物多様性』養賢堂、1998年3月)。それらは、①生態系サービス(物質循環、環境浄化機能);②有用資源価値(食用・農業用資源、医学・薬学的価値など):③アメニティ価値(快適性、景観形成、スポーツ・レジャー用価値など);④教育的・文化的価値(グリーン・ツーリズム、園芸療法など)である。
しかし、1960年代に始まる農業の近代化で里山および水田の生物多様性を取り巻く状況は一変した。農地のほ場整備、大型機械の導入、化学資材の多投入、用水と排水の分離、用水路のコンクリート化などによって、多くの野生生物たちの棲み処は失われ、生物の多様性も喪失することとなったからである。同時に、都市化の波や無秩序な宅地開発によって農村のすぐれた環境や景観もかなり悪化してきたのである。
水田や里山における生物多様性に着目した取り組みは、これらの一連の反省の中から生まれてきたものである。全国各地で、豊かな農村景観や里山の生き物たちを取り戻したいという、さまざまな取り組みが始まり、全国に広がりつつある。農業生産のあり方を見直し、環境保全型へと変えようという現場での運動とともに、農業政策もようやく大きな転期を迎えたのである。
2010年に名古屋市で開催されるCOP10(生物多様性条約第10回締約国会議)では、里山・里海の価値を含めて、生物多様性のもつ価値と利活用について国際的に議論がかわされることになろう。思い起こせば、1992年の地球サミット「アジェンダ21」に基づいて、生物多様性条約がスタートした。日本も直後にこの条約に署名し、1995年10月には生物多様性国家戦略を策定した。これは単に絶滅危惧種の保護や遺伝子の保存という問題にとどまらず、身近な生物の大切さや環境保全と調和する農業のあり方を推進する契機ともなっている。
農業と環境とのかかわりについて、今後、私は次の3つの見直しが求められると考えている。
1つは、農業生産技術のあり方の総点検であり、その「安全証明」が求められていることである。健康な土や水が健全な農産物を作り出し、それを食することで人は健康になれるのだという関係性を明確にすることが大切であろう。いかなる技術や生産方法によって環境調和型の農業が実現し、その結果どう変わるのかという、一種の安全証明が求められている。できれば、農産物の市場評価がその安全証明とセットで行われることが望ましい。
2つ目は、地域の足元から農業と環境のつながりを見直すことの重要性である。川下側あるいは消費者との連携、協力が不可欠であり、また、地場産の農産物を適正に評価するシステムが必要となる。それは産地側からみれば、独自のマーケティング戦略が重要だということを意味している。いかに生産者が技術的な努力を重ねても、消費者による評価が低ければ経営的に成り立たないからである。国際競争が当たり前となった今、価格・コスト面の競争では、国産農産物は輸入品に勝てない。やはり品質と安全性の両面から国際競争すべき時代であり、環境の価値をいかに川下に伝達するかが成否のカギを握っていると思われる。
3つ目は、環境問題を食生活の視点から捉えることである。農業の問題をわれわれの栄養や健康の問題とつないで考え、食品の安全・安心を足元の農業のあり方と関連付けて捉えることの大切さを強調したい。このように、食・農・環境という3つの連鎖の中から足元の農業を見直し、地域環境や生物多様性という価値を顕在化させたいものである。
(付記)本稿は、拙著『食卓からの農業再生』(家の光協会、2009年2月)より抜粋、一部加筆したものである。
- 国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)
- 国立研究開発法人森林総合研究所(FFPRI)
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構(FRA)
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)
- 国土交通省気象庁気象研究所(JMA)
- 国土交通省国土技術政策総合研究所(NILIM)
- 国立研究開発法人建築研究所(BRI)
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所(PARI)
- 国立研究開発法人土木研究所(PWRI)
- 国立研究開発法人国立環境研究所(NIES)
- 国立大学法人筑波大学